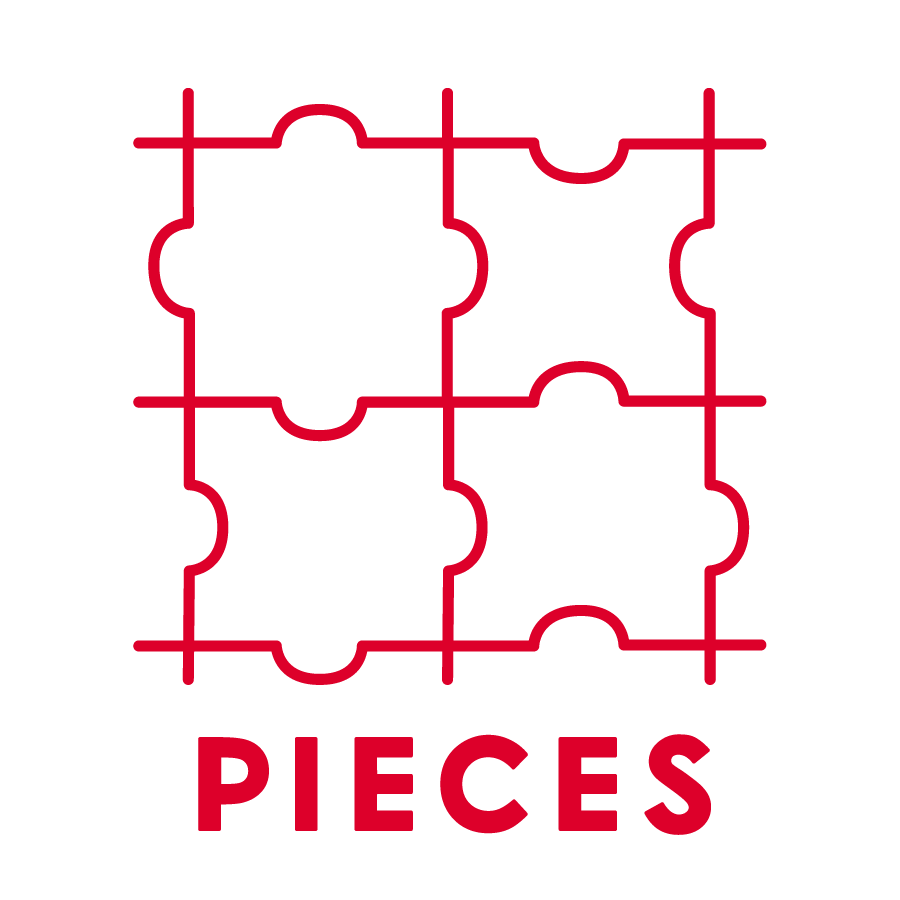現在、アジアでは、make funを合言葉に、国を超えて市民同士が市民性を通して非暴力的な方法で協働・連携するいったうねりが、今回のミャンマーの動きに象徴されるように起きています。その非暴力の民主化運動の広がりの過程において、市民自身が自分たちの消費行動を問い直したり、活動に必要なものをお互いに補完しあったり、助けが必要な時に助け合うと言った市民性を通した繋がりやエンパワメントが生まれています。
私たちは、このことを決して遠い誰かのことではない自分たちにも関わることだと考えています。
日本においても基本的人権や尊厳が侵害される状況はまだ存在し、そこに対してなんとかしようとしている国内外の人たちがいます。
だからこそ、今回、私たちは、地球上に共に生きる人として、「市民性」を自分たちの実践を通して社会に開き、働きかけていくこと、「ひらかれたwe」というあり方を自分たちが実践することを軸として今回の判断をしました。みなさんと一緒に一人の市民として見つめて、受け取り、対話をし、働きかけていくといった市民性を、日本社会においても、さまざまな組織や人たちと共に耕していけたらと考えています。
※補足1※
「ひらかれたwe」は、PIECESで紡いだ言葉です。それは、私という存在が、社会や地球環境と相互に響き合うような「we」の感覚をもって社会で起こることを捉え、応答していく。つねに他者や環境へ「ひらかれた」状態にあり、お互いに影響しあい、揺れ動きながら存在していることを感じながら物事を見つめ、受け取り、働きかけていくあり方のことを指します。
今回、私たちは、ミャンマーの市民社会の人権を守るための声明の呼びかけ団体になりました
呼びかけ団体になるにあたり、以下の3点について検討しました。
1)PIECESのミッションである市民性醸成に即すものであるか。
2)本件に対して声をあげることが、市民社会において大切な基盤となる、社会としての基本的人権や尊厳の尊重、充足を促進するプロセスにつながるか。
3)ミャンマーの市民社会にとって、声明で要求する内容が基本的人権の侵害を助長する可能性はないか。また、ミャンマーの市民が望む社会と相反していたり、道のりを阻害する可能性はないか。
これらの点について、私たちは以下のように考えています。
1)現在、ミャンマーでは深刻な人権の侵害が行われています。同じ時代に国や民族、思想や宗教を越えて共にこの地球に生きる市民の切なる声を受け取った私たちが、そのことに応答していくこと。それは、私たちPIECESが大切にするに市民性そのものであり、そのあり方、態度を示すことが私たちなりの市民性の発揮の仕方であると考え、今回声をあげるという判断をしました。
※補足2※
私たちの考える市民性は、物質の所有や消費、あるいはイデオロギーや特定の価値観に自分の人生の主導権を握らせることなく、自分自身の願いに目をむけ、自分の時間を生きることを通して、社会に働きかけていく態度や作法のことをいいます。これは、自分自身の感情、目の前にいる相手の言葉や表情、自分が暮らす地域の営み、事件や紛争、気候や自然環境の変化ー私たちが生きる社会に起こるさまざまな事象を、ありのままにみつめようとすること、私たちがつながりや相互作用の中に生きていることをに身を置き、気づかずにいたさまざまなことを受け取ること、すでにあった新たなことを受け取った一人ひとりが、さまざまな存在と影響しあっていることを意識しながら世界にはたらきかけ、多層的に循環を生んでいくということでもあります。
・市民性についての詳細はこちらをご覧ください。
2)市民社会における人権の侵害に対して、反対の意思を示し、基本的人権とは何か、尊厳とは何かを問い、対話し、自分たちのこととして手元からそれらを紡いでいくことが、基本的人権の尊重と充足のプロセスに協働し、市民社会のエンパワメントしていくことにつながると考えました。
3)一方で、すべての事柄を実行するには、作用と反作用があります。そこで、今回声明で要求する各論に関して、ミャンマーの市民に対して及ぼす影響についても考えました。たとえば、経済的制裁がもたらされるかもしれないことによる影響、孤立化により起こりうる国家体制への影響について、複数の人へのヒアリングや、実際ミャンマーの市民との繋がりのある人の声などを聴きながら検討しました。
実際、これがどのような影響となるかの正解がないからこそ、自分たちのあげた声が短期的、長期的にどのような影響を及ぼすのかをきちんと見つめ、実際の現地の方の声を聴き、発起団体の方々、また葛藤があるからこそ声をあげないという選択をした方々と試行錯誤していきたいと考えています。
以上を踏まえて、今回呼びかけ団体に加わりました。
(以下、声明全文)