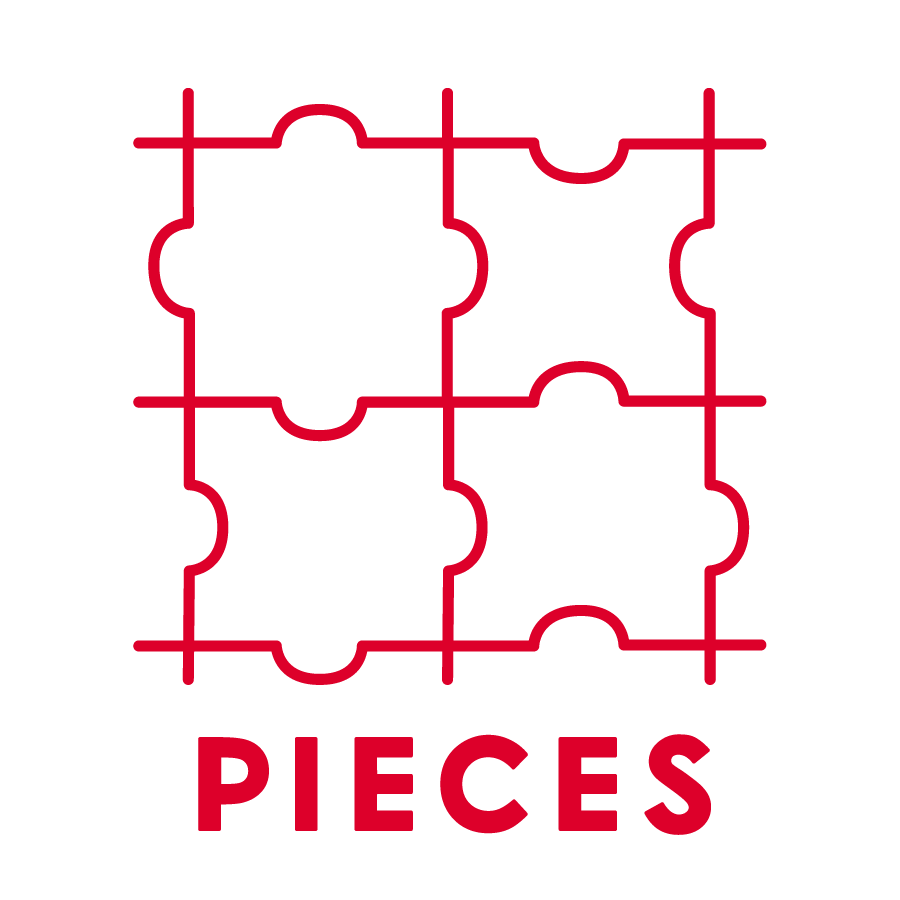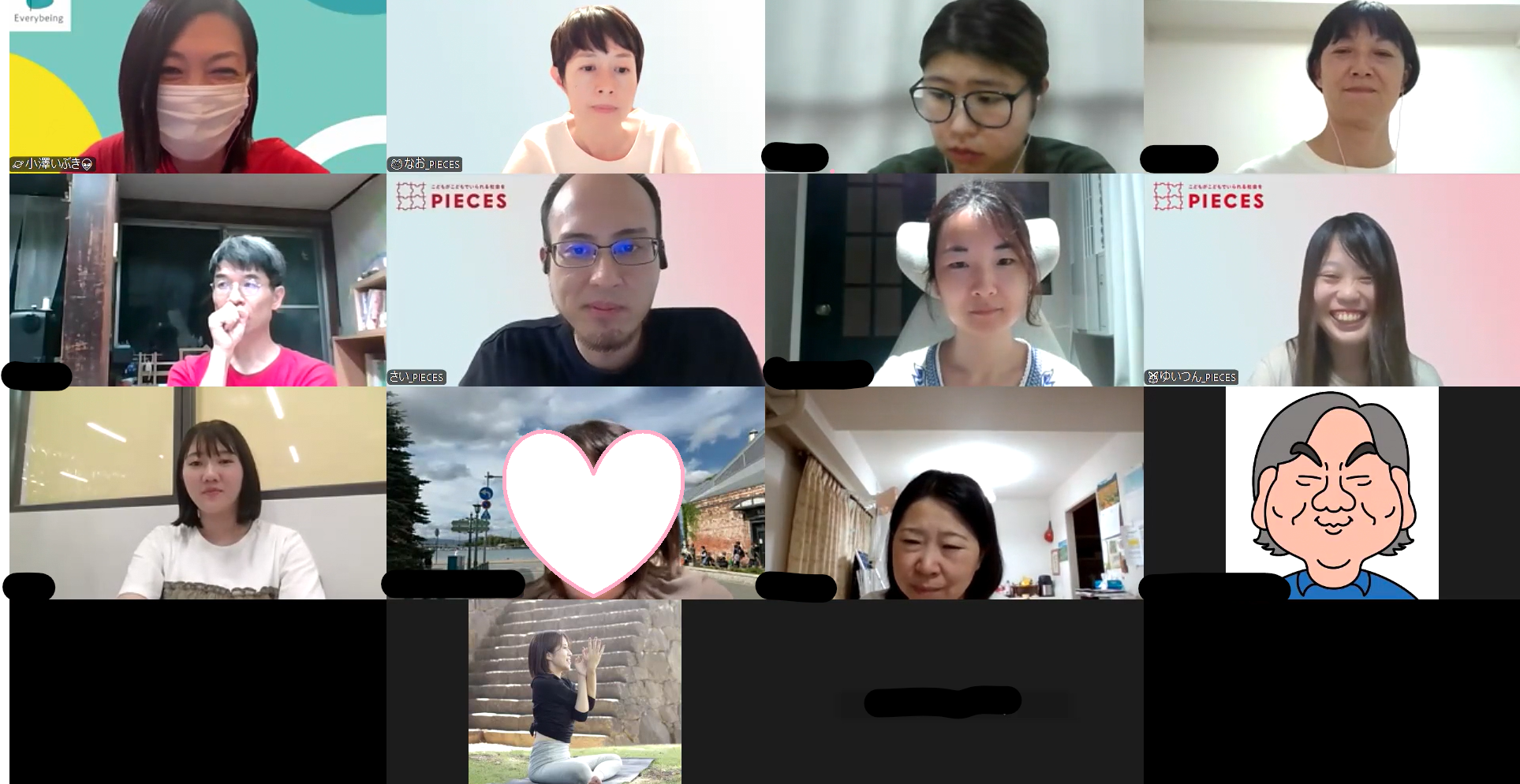子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムCitizenship for Children2024
「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。
今年度の募集広報期間を経て、CforC2024は基礎コース3名、探求コース10名、動画コース6名にご参加いただき、プログラムをスタートしました!
初回は9月18日に講師を囲む会、9月21日に対面ゼミを実施しました。
講師を囲む会
参加者には、事前に2つの講座動画を視聴してきてもらいました。
「子どもの発達と心のケア ~児童精神科医の視点からみえる、子どもたちの今〜」
講師:小澤いぶきさん(NPO法人PIECESファウンダー/一般社団法人Everybeing共同代表/児童精神科医/こども家庭庁アドバイザー)
①子どもを取り巻く現状
②子どもの発達の基盤となる安心・信頼の醸成
③子どもの発達に影響するもの
④子どもが子どもでいられる社会であるために
「わたしたちの中にある「市民性」を見つめる」
講師:斎典道さん(NPO法人PIECES代表理事/ソーシャルワーカー)
①なぜいま、「市民性」なのか?
②市民性の発揮と「優しい間」の創出
2つの講座を通して、子どもを取り巻く環境について様々な角度から学ぶことができました。そのうえで、子どもにとって安心できる関わりはなにか、ひとりの人としてなにができるのかという問いが生まれたように感じています。
参加者から講師に投げかけられた疑問や葛藤を一部をご紹介します。
・一人の人としてかかわるときに、どういう感覚を持って接しているのか。
・中高生の自尊心を育む接し方について、こういう考え方が大切だと考えられるものはあるか。
・専門性と市民性は対極にあるものなのか。専門性を持って活動する人のなかにも市民性があり、市民性を持っている人のなかにも専門性があるということなのか。
質問に対する講師からのコメントも、正解の提示ではなくひとつの視点として、講師と参加者との対話が繰り広げられました。今回は少人数だったため、一人ひとりの声を聴きながら、対話していくことで自分の価値観が揺さぶられたり、様々な感情が生まれていく、とても豊かな時間となりました。
ゼミ活動
9月21日は、東京と大阪の2つの会場で参加者が対面で丸1日集まり、ゼミ活動を行いました。今年度のゼミ活動は、東京クラスは10名、大阪クラスは3名の参加者と、それぞれ修了生やプロボノといったピアサポで、同時間帯に2会場で同じプログラムを行うという初めての試みです。
第1回目のゼミは「学びあいの土台をつくる」をテーマに次の内容を行いました。
安心・安全な環境づくりのワーク
お互いを知り、“学び合い実践するコミュニティ”の基盤をつくるため、CforCにたどり着くまでのストーリーを語る
市民性のメガネをかけながら、街歩き
自分自身や自分の周囲に既にある価値観のメガネ
昨年まではオンラインで行っていたプログラムですが、今回は少人数での対面開催ということで、発する言葉だけでなくその人の仕草や行動や様子など、一人ひとりの存在をリアルに感じることができました。今後みんなで過ごしていくプログラム期間がとても楽しみになりました。
参加者の感想 うっちー(探求コース)
他の参加者の方がどのような過程を辿ってCforCに辿り着かれたのかをみんなで輪になり、語り合うパートが印象的でした。
相手の立場になって考えることを示す「他者の靴を履く」という言葉がありますが、皆さん一人一人のストーリーをお聞きして、聞く前と比べて皆さんから発させる言葉の背景が少しだけ見えるような気がしました。それもまた主観的解釈に過ぎないとはいえ、分かりやすく見える人の振る舞いだけでなく、その人の価値観・願いの部分まで知って初めて「他者の靴を履くこと」が出来るのであってその行為は決して容易くはないのだなと実感しました。
他者の立場に立つという行為は相当な相手への関心やオープンな相互コミュニケーションが無ければ真の意味では達成されてないと思っていたので、やっぱりそうだよなぁと納得させられました。相手の立場に立とうと考えたその時に、自分が相手の価値観や願いまでを考慮した上で考えられているのか(色眼鏡をかけてしまっていないか)を意識していきたいと思います。
CforC2024では今後も、様々なフィールドで子どもと関わる実践者や専門家の方を講師に招き、参加者同士の対話やワークを通して、子どもと自分にとっての心地よいあり方をみんなで探していきます。
執筆:スタッフ 西角綾夏