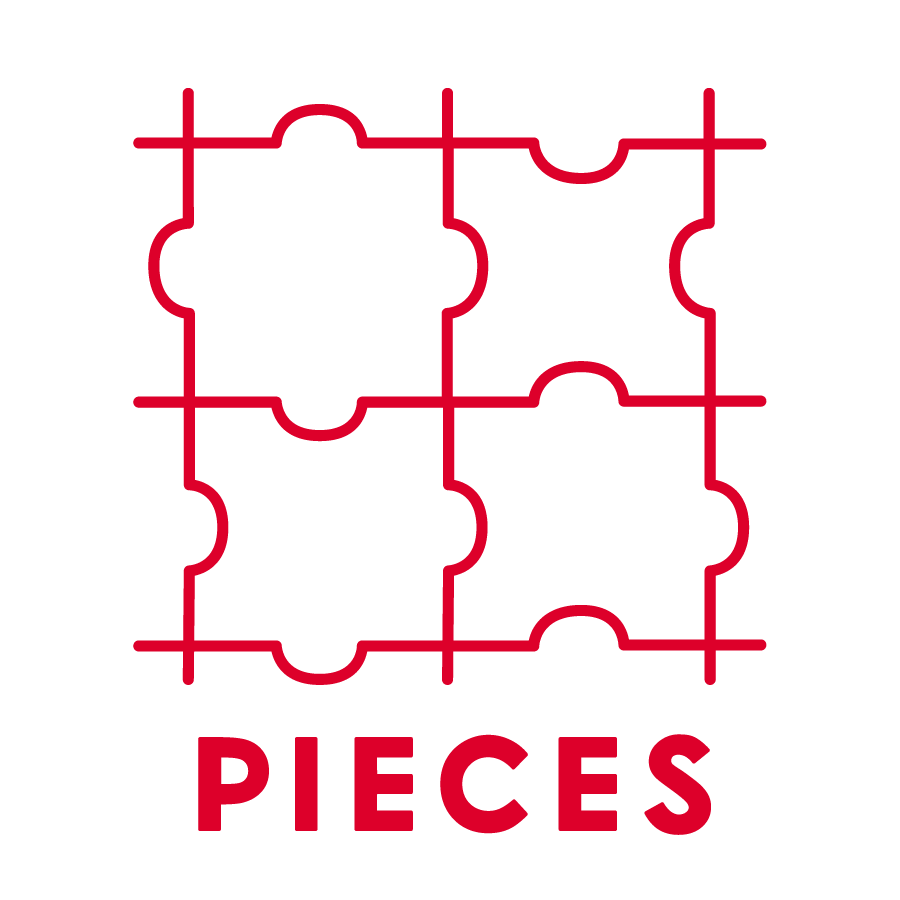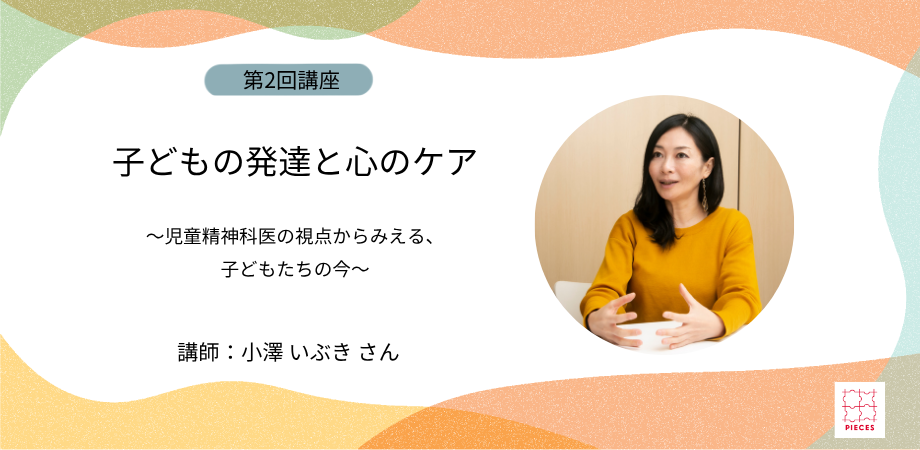子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムCitizenship for Children2025
「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。
今年度のCforCは、「講座」「リフレクション」「アクションサポート」というコンテンツを参加者が自由にカスタマイズできることが特徴です。(各コンテンツあわせて現在19人が参加しています。)
その中で、「講座」に参加している方がリアルタイムで集まり、事前に視聴した講義動画をもとに講師との質疑応答や対話を行う、講師を囲む会を8月27日に開催しました。
講義動画概要
■講師:小澤いぶきさん
NPO法人PIECESファウンダー/一般社団法人Everybeing共同代表
児童精神科医/こども家庭庁アドバイザー
■講座タイトル
子どもの発達と心のケア ~児童精神科医の視点からみえる、子どもたちの今〜
■主なトピック
① 子どもを取り巻く現状
② 子どもの発達の基盤となる安心・信頼の醸成
③ 子どもの発達に影響するもの
④ 子どもが子どもでいられる社会であるために
講師を囲む会
参加者には、事前に下の講座動画を視聴していただきました。
講師の小澤さんは最近、沖縄の多良間島という自殺希少地域で数日間を過ごされたそうです。その中で感じた島の人たちとの関わりから「市民性の層が厚い」と感じたことをお話してくださいました。
参加者からの質問は、その具体的なエピソードを知りたいという内容から始まりました。
その後も、
「自分が大人の価値観を押し付けていないかをどのように自覚するにはどうすればよいのでしょう」
「現在、日本では少子化が進む一方で、子どもの孤立が益々深まっているように感じる。
さまざまな要因が考えられる中で、その一因として『自然災害』や『気候』などの自然環境がもたらす影響にはどのようなものがあるでしょうか」
などの質問が続き、小澤さんからの回答だけではなく、気づきのシェアやみなさんの対話がありました。
今回、小澤さんがお話の参考に案内された note と書籍
note(自殺希少地域に暮らす子どものまなざし)
紹介書籍(異常気象や戦争、震災といった非日常が心に及ぼす影響)
参加者の感想
被支援者を勝手に作らない。「一緒にどんな風景を見たいか」という問いに戻りたいなと思いました。
子どもにも敬意をもって1人の人として関わるということを大切にしたいと思った。
(執筆者 CforCプログラム担当:泉森奈央)
CforC2025では、参加者同士の対話やワークを通して、子どもと自分にとっての心地よいあり方をみんなで探求しています。現在、10月31日まで後期講座参加者を募集しています。ご興味のある方は、講座申込ページをご覧ください。